知る・理解する・行動することで適切な対応力を 令和7年度 青年部全国研修会 開催される
 7月17日、大阪市で「令和7年度 青年部全国研修会」が開催されました。全国各地から青年部会員や役員が参集し、研修に臨みました。
7月17日、大阪市で「令和7年度 青年部全国研修会」が開催されました。全国各地から青年部会員や役員が参集し、研修に臨みました。意見発表では、同和教育のあり方や地域活動を通じての活動、行政との関わり方や同和運動を行う上での知識や能力の向上など、また運動団体としての資質を高めてゆくことなどが論じられ、研修会開催の重要性を深く再認識しました。
大阪市中央区のドーンセンターで開催された研修会には、都連から古賀会長・東青年部長をはじめ、多くの都連役員・青年部部員が参加しました。
午前十時三十分、関裕雅全国青年部理事(神奈川県連)の司会で始まった研修会では、髙木剛全国青年部副部長(大阪府連)が開会の言葉で、「地域によっては、同特法時代に同和地区が指定されなかった所もあります。同和地区が存在しないから部落差別は生じないなどという考えから、同和問題に積極的に取り組んでいない自治体もあると聞いています。しかし、同和地区が存在しないことを理由に、同和問題に取り組まなくて良いという考えは、明らかに間違っています。同和問題の完全解決を期すには、家庭教育、学校教育、社会教育を推進してゆくことが必要不可欠であり、国、地方自治体の果たす役割は重要です。こうした認識の下、我々青年部は部落差別解消推進法が具現化されるよう、行政に対し強く求めてゆかなければなりません。そのために、研修や実践に学び正しい理論を身につけなければなりません」と、研修会開催の意義を込めた開会の辞を述べました。
荒井正記大阪府連会長は開催府連会長挨拶で、「同和問題はヒューマニズムの問題であり、民主主義の課題です。国、地方自治体、民間を動かすには、提言活動や支持される運動が重要です。そのために、組織の強化、知識力、探究心を高めることにより、提言活動が行え、また支持される組織となり得、組織の拡大に繋がります。青年部の皆さんには、知性と理性を持ち、日々運動に邁進して頂きたい」と奮起を促しました。
全国会長挨拶の中で松尾信悟全国会長は、「同和問題の解決を図るため、特別措置法に基づき各般にわたる諸政策が行われ、生活環境に関する整備は一定の成果を上げ大きく改善されました。しかし、結婚や就職問題を中心とする心理的差別は、未だ後を絶ちません。更に、インターネットを利用した不適切発言により、差別を助長するような動画発信も増えてきており、差別を抑制するための法整備が急務となります。全日本同和会は昭和35年の結成以来今日まで『子らにはさせまい この思い』をスローガンに、運動を推進してきており、これからも創立の原点に立ち返り襟を正し自己の役割と使命感を深く自覚し、同胞一和の精神で、運動を継続してゆかなければなりません」と、研修会開催の必要性を訴えました。
関寅明全国青年部部長は挨拶で、「同和問題を取り巻く環境は、結婚、就職問題のみならず、SNSを使用した差別事象など、ソフト面における人権侵害事案が起きており、匿名性が高いことも相まって、陰湿かつ複雑化しているのが現状です。この陰湿かつ複雑化してゆく現状に対し、我々運動団体の取り組み方も、多岐にわたり求められています。その中で一つでも多くの市区町村での、部落差別に対する条例の制定が部落差別の完全解決には必要です。各都道府県の政策のあり方や折衝の仕方には、各都道府県ごとに特色があり苦労されていると思いますが、青年部の皆さんは力を併せて運動に邁進してゆきましょう」と表明しました。
祝電披露に続き、基調講演へと移りました。
基調講演は、大阪市立大空小学校初代校長の木村泰子氏により、『「みんなの学校」が教えてくれたこと』と題し、一時間に亘りなされました。
午後の部では、代表県連による意見発表が行われ、今年度は福岡県連合会と茨城県連合会が発表しました。
意見発表を受けて、土肥孝明全国青年部副部長(福岡県連)が総評を行いました。土肥副部長は、「一度根付いた偏見や固定観念を解消するには、時間と努力、継続的な教育、啓発活動が必要です。人権侵害や差別問題は、一朝一夕で解決できるものではありません。社会全体で一人ひとりの意識を変える為に、教育現場だけではなく、多方面からの継続的な取り組みが必要不可欠です。わたしたち一人ひとりが自覚と責任を持ち、多様性を尊重する社会づくりに向けて、努力してゆかなければなりません。また、同和問題に対する正しい認識を持つために、過去の差別や偏見、制度についても深く知る必要があります。知る、理解する、行動するの三つのステップを踏むことで、同和問題に対する正しい認識と適切な対応力が養われます。このプロセスを意識することで、多様性と共生社会への道筋が開かれ、真の差別撤廃へと繋がり、お互いが尊重し合える社会実現への第一歩になると思います。
全日本同和会は、対話と協調を基本理念とし、「子らにはさせまい この思い」をスローガンとし、差別の無い共生社会の実現に向け、住民、行政が一体となり、差別解消に取り組んでゆくことが必要です」と、両県連の意見発表を総評しました。 谷川高廣全国青年部副部長(京都府連)によるスローガン採択の後、千村啓喜全国青年部副部長(東京都連)が、「本年2025年は、日本で普通選挙法案が成立して100年となります。正確な意味では、女性の参政権が認められていなかったので、現在では、一般に男子普通選挙と呼ばれるものです。しかし、一般民衆の自由を恐れるあまりか、政府は同時に治安維持法も発令しており、厳しい人権弾圧の時代への始まりとなりました。女性の参政権が認められたのは終戦直後であり、外圧によってもたらされたものであると言ってよいと思います。長い歴史を見渡しますと、我々が推し進める同和問題の解決も、如何に政治に翻弄されてきたかが分かります。生身の人間の人権が、政治の思惑に左右されて良い筈はありません。イデオロギーに左右されない我々全日本同和会こそ、このような悪しき歴史から脱却する中心的役割を果たすべき存在であると思います。
その中で、青年部は、同和会全体の中でも最も活力ある運動の推進エネルギーとなる存在であると、自負しております。あらゆる差別を無くすために奮闘しておられる全国の同志の皆様の引き続きのご支援とご協力を切にお願いして、閉会のご挨拶とさせていただきます」と閉会の辞を述べ、研修会は終了しました。
(青年部全国研修会の詳細は、都連発行機関紙「東京あけぼの 9月号」に収録されています)
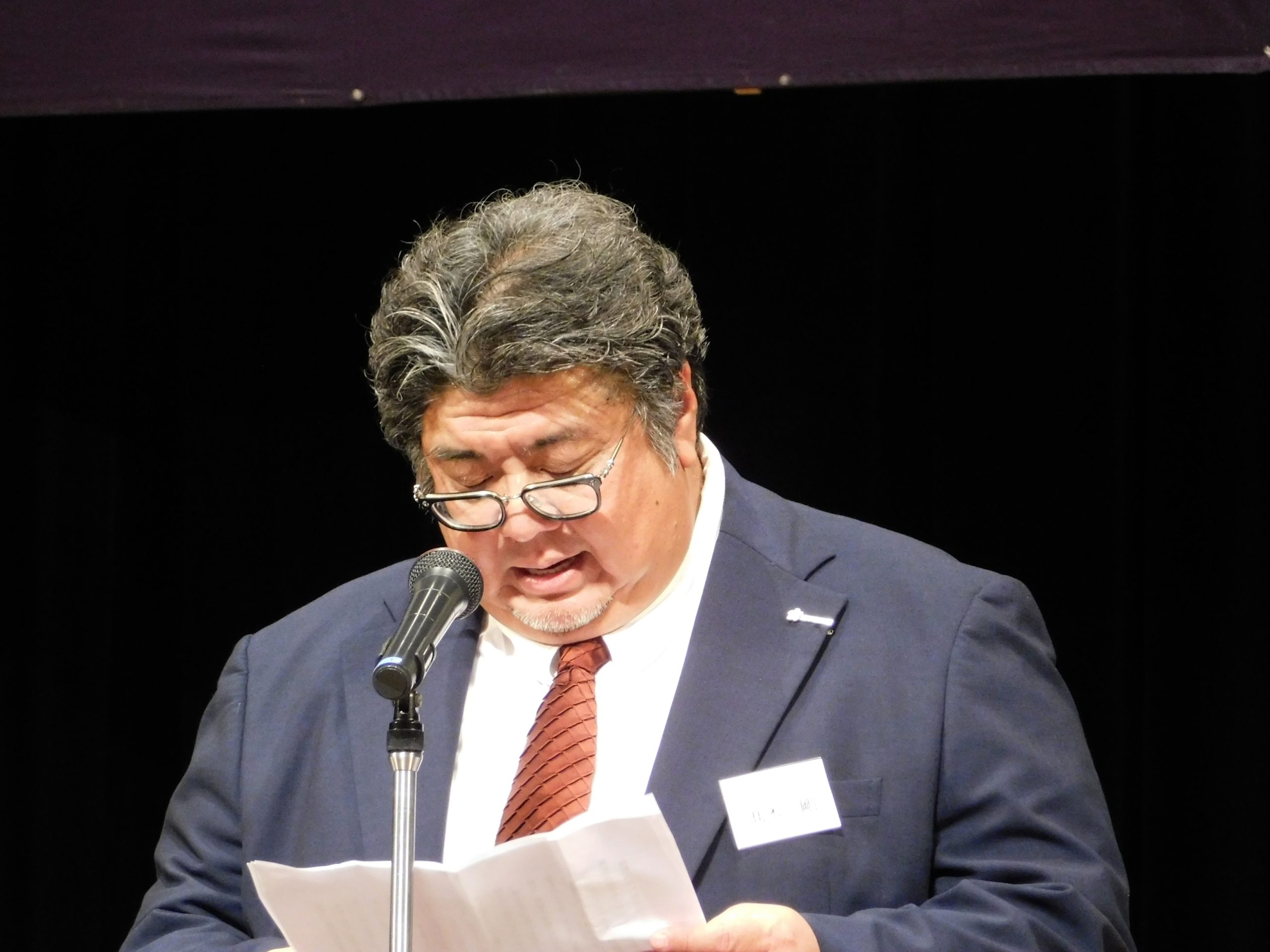
開会の言葉 髙木剛 全国青年部副部長

開催地県連挨拶 荒井正記 大阪府連合会会長

全国会長挨拶 松尾信悟 全国会長

全国青年部長挨拶 関寅明 全国青年部長

総評 土肥孝明 全国青年部副部長

スローガン採択 谷川高廣 全国青年部副部長

閉会の言葉 千村啓喜 全国青年部副部長
